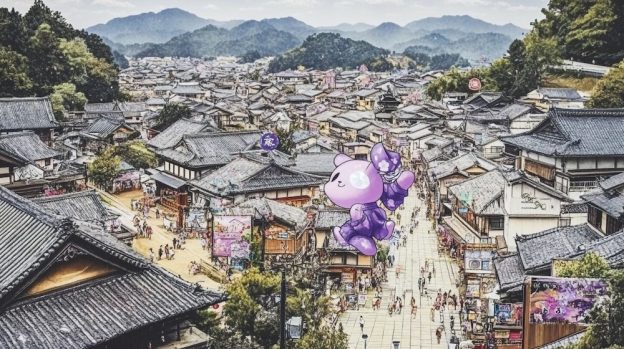「地元はどこ?」。
東京で暮らしていると、そんな会話がふとした瞬間に顔を出す。
わたしにとって、その答えはいつも「新潟」だ。
新潟。
その響きに、どんなイメージを抱くだろうか。
米どころ、酒どころ、雪国、日本海……。
どれも間違いではないけれど、わたしにとっての新潟は、もっと個人的で、もっと手触りのある記憶と結びついている。
この街で生まれ育ち、大学進学を機に東京へ。
Webメディアの編集部でインターンを経験し、文章を書くことを仕事にしてからも、心のどこかにはいつも新潟の風景があった。
それは、わたしの「書く」ことの原点なのかもしれない。
この記事では、わたし、松井里音がなぜ新潟という街に惹かれ続けるのか、その理由を7つの視点から綴ってみたい。
それは決して、きらびやかな観光案内ではない。
むしろ、日常の延長線上にある、ささやかだけれど愛おしい「好き」のかたち。
そして、その「好き」を包む、新潟ならではの空気感のようなものを、少しでも感じ取ってもらえたら嬉しい。
1. 静けさの中にある強さ —— 雪の朝の記憶
新潟の冬を語る上で、雪は欠かせない存在だ。
それは時に厳しく、生活に大きな影響を与えるけれど、同時に、他では味わえない特別な時間をもたらしてくれる。
雪がもたらす時間のゆるみ
しんしんと雪が降り積もる夜。
窓の外は、いつもよりずっと静かで、時間がゆっくりと流れていくような感覚に包まれる。
車の音も、遠くの喧騒も、分厚い雪の層に吸い込まれていく。
それはまるで、世界から一枚、薄いベールをかけられたような、不思議な安心感。
慌ただしい日常からふっと解放されて、心がおだやかになるのを感じる。
生活音の消えた街の美しさ
翌朝、カーテンを開けると、そこには一面の銀世界が広がっている。
生活音が消えた街は、いつもとは違う表情を見せる。
屋根も、道も、木々も、すべてが等しく白い雪に覆われて、まるで知らない場所に迷い込んだかのようだ。
「雪国であった。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」
川端康成の『雪国』の冒頭はあまりにも有名だけれど、あの感覚は、雪国で育った者なら誰しもが共感できるのではないだろうか。
すべてをリセットするような、潔いまでの白。
その美しさに、いつも息をのむ。
何度も書きたくなる「白」の風景
雪の白は、ただの一色ではない。
朝日に照らされてきらめく白。
曇り空の下で、どこまでも続くように見える、静謐な白。
夜の街灯にぼんやりと浮かび上がる、幻想的な白。
そのどれもが、わたしにとっては特別な「白」の風景だ。
何度文章に書こうとしても、その感動を完全には写し取れない。
だからこそ、また書きたくなるのかもしれない。
雪が降るたびに、あの静けさと美しさを、誰かに伝えたくなるのだ。
2. 地元スーパーと、日常のごちそう
旅先で市場やスーパーに立ち寄るのが好きな人は多いと思うけれど、わたしにとって新潟の地元スーパーは、まさにそんな心ときめく場所の一つだ。
そこには、日常に溶け込んだ「ごちそう」が溢れている。
小さな買い物に宿る文化
例えば、夏になると必ず買うのが「もも太郎」というアイス。
いちご味のかき氷バーで、新潟県民なら誰もが知っているソウルフードだ。
派手さはないけれど、あの素朴な甘さが、夏の訪れを感じさせてくれる。
他にも、棚に並ぶ醤油の種類が豊富だったり、「かんずり」のような地元特有の調味料が当たり前のように売られていたり。
そんな小さな発見の一つひとつに、その土地ならではの食文化が息づいているのを感じる。
新潟の食卓を彩る定番たち
- 栃尾の油揚げ: 肉厚でジューシー。焼いて生姜醤油で食べるのが定番。
- へぎそば: 布海苔(ふのり)をつなぎに使った、つるりとした喉越しが特徴の蕎麦。
- タレかつ丼: 揚げたてのカツを甘辛い醤油ダレにくぐらせた、新潟市発祥のご当地グルメ。
- のっぺ: 里芋、人参、こんにゃく、鮭などを煮込んだ郷土料理。お正月やお祭りの定番。
これらはほんの一例だけれど、地元スーパーの棚を眺めているだけで、新潟の食卓の豊かさが伝わってくる。
地元食材との再会がくれる安心感
東京のスーパーでも、もちろん美味しいものはたくさん手に入る。
けれど、新潟のスーパーで馴染みのある食材や商品を見つけると、なんだかホッとする自分がいる。
それは、味覚を通して呼び起こされる記憶であり、故郷とのつながりを再確認できる瞬間なのかもしれない。
新鮮な地元の野菜、日本海の魚介、そして何よりも美味しいお米。
それらが当たり前に手に入る環境は、離れてみて初めてそのありがたみに気づくものだ。
3. 誰かの「ただいま」が似合うまち
新潟の街を歩いていると、ふと「ただいま」という言葉が自然と口をついて出そうになる瞬間がある。
それは、そこに住む人々の温かさや、街全体を包むどこか懐かしい雰囲気がそうさせるのかもしれない。
商店街と人との距離感
特に、昔ながらの商店街を訪れると、その感覚はより一層強くなる。
八百屋のおじさんとの何気ない会話。
魚屋さんの威勢のいい声。
豆腐屋さんの、出来立ての湯気が立ちのぼる様子。
そこには、大型スーパーにはない、人と人との直接的な触れ合いがある。
「今日はこれがおいしいよ」「おまけしとくね」。
そんなやり取りが、日常の風景として当たり前に存在している。
上古町商店街の風景
新潟市中央区にある「カミフル」こと上古町商店街は、わたしのお気に入りの場所の一つだ。
レトロな雰囲気のアーケードが続くこの商店街には、古くから続くお店と、新しい感性のお店が程よくミックスされている。
ただ商品を売買するだけでなく、そこには店主とお客さんとの間に、ゆるやかで心地よいコミュニケーションが生まれているように感じる。
すぐに会える親戚のような関係性
新潟では、少し歩けば知り合いに会う、なんてことがよくある。
それは、都市の規模感がちょうど良いからなのか、それとも地域コミュニティがまだ色濃く残っているからなのか。
「あら、里音ちゃん、久しぶりねぇ」。
そんなふうに声をかけられると、まるで親戚のおばちゃんに会ったかのような安心感を覚える。
東京ではなかなか感じることのできない、この「顔の見える関係性」が、新潟の大きな魅力の一つだと思う。
それは、決して馴れ合いという意味ではなく、お互いをゆるやかに気遣い、見守り合っているような、そんな温かい距離感なのだ。
4. “地味”がくれる自由と余白
「新潟って、ちょっと地味だよね」。
そんなふうに言われることがある。
確かに、東京や大阪のような大都市と比べれば、刺激的なものは少ないかもしれない。
けれど、わたしはその「地味」さが、新潟の大きな魅力だと感じている。
派手じゃないからこそ、自分で色を足せる場所
派手なランドマークや、常に新しいものが生まれ続ける喧騒がない代わりに、新潟には「余白」がたくさんある。
それは、自分で何かを見つけたり、創り出したりする自由を与えてくれる。
例えば、何もないと思っていた田んぼ道も、よく見れば季節ごとに美しい草花が咲いていたり、夕焼けが空をドラマチックに染め上げたりする。
誰かに与えられる刺激ではなく、自分で見つける小さな感動。
そんな瞬間に、心が豊かになるのを感じる。
比較されにくいからこその生きやすさ
情報が溢れ、常に誰かと比較されがちな都会の生活。
それは時に、自分を見失いそうになるほどのプレッシャーを与えることがある。
その点、新潟の「地味」さは、いい意味で他者からの過度な干渉や評価から距離を置かせてくれる。
自分のペースで、自分の好きなものに囲まれて暮らす。
そんな、地に足のついた生き方がしやすい環境なのではないだろうか。
「地味」のポジティブな側面
| 地味と言われる特徴 | ポジティブな捉え方 |
|---|---|
| 刺激が少ない | 落ち着いて物事に取り組める、内省的になれる |
| 目新しさがない | 普遍的な価値観を大切にできる |
| 流行に疎い | 自分の「好き」を追求しやすい |
| 人が少ない | 穏やかな人間関係を築きやすい |
もちろん、これはあくまでわたし個人の感じ方だ。
けれど、この「地味」さがくれる自由と余白が、わたしにとってはとても心地よい。
5. 水と空のグラデーション —— 新潟の景色
新潟の風景を思い浮かべるとき、そこにはいつも「水」と「空」がある。
日本海、信濃川、そしてどこまでも広がる空。
それらが織りなす美しいグラデーションは、わたしの心象風景と深く結びついている。
日本海の夕暮れ
新潟の日本海に沈む夕日は、何度見ても言葉を失うほど美しい。
空と海がオレンジ、ピンク、紫へと刻一刻と色を変えていく様は、まるで壮大な絵画のようだ。
特に、佐渡島に夕日が重なる瞬間は、息をのむほどの絶景。
水平線に吸い込まれていく太陽を見送るとき、日々の悩みや疲れがすーっと浄化されていくような気がする。
この夕景を見るためだけにでも、新潟に帰る価値があると思うほどだ。
信濃川沿いの散歩道
日本一長い川、信濃川。
その雄大な流れは、新潟の街に豊かな恵みをもたらしてくれる。
川沿いには整備された散歩道があり、市民の憩いの場となっている。
春には桜並木がトンネルを作り、夏には緑が目に鮮やかで、秋には紅葉が水面を彩る。
そして冬には、雪化粧した静かな風景が広がる。
季節ごとに表情を変える信濃川沿いを散歩するのは、わたしにとって最高のリフレッシュ方法の一つだ。
空気のにおいでわかる「帰ってきた感」
新幹線を降りて、新潟駅のホームに立った瞬間。
あるいは、車で関越トンネルを抜けた瞬間。
ふっと感じる、あの独特の「空気のにおい」。
それは、湿り気を帯びた土のにおいだったり、潮の香りだったり、あるいは雪の気配だったりする。
言葉で表現するのは難しいけれど、そのにおいを嗅ぐと、「ああ、帰ってきたんだな」と実感する。
五感で感じる、故郷のしるし。
この「帰ってきた感」は、何物にも代えがたい安心感を与えてくれる。
6. 東京から見えてきた新潟の輪郭
大学進学で新潟を離れ、東京で暮らし始めてから、故郷である新潟の輪郭が、以前よりもはっきりと見えるようになった気がする。
それは、物理的な距離が生まれたからこそ得られた視点なのかもしれない。
離れて初めて気づいたこと
当たり前だと思っていた日常の風景や、地元の人々の温かさ。
それらが、実はとても貴重で、かけがえのないものだったということ。
離れてみて初めて、その価値に気づかされることは多い。
例えば、新潟の食べ物のおいしさ。
お米はもちろん、野菜も魚も、そして水も。
東京でも美味しいものはたくさんあるけれど、新潟で食べる地元の食材の味は、やはり格別だと感じる。
また、ゆったりとした時間の流れや、豊かな自然がすぐそばにある環境も、東京の喧騒の中で暮らしていると、より一層そのありがたみを感じる。
地方を照らす視点としての原風景
コンテンツ制作の仕事を通して、「東京から見る地方」という視点に触れる機会は多い。
けれど、わたし自身が新潟という「地方」で育った経験は、「地方から照らす東京」あるいは「地方から見つめる別の地方」という、また違った視点を与えてくれる。
それは、決してどちらが良い悪いという話ではない。
それぞれの場所にそれぞれの魅力があり、それぞれの課題がある。
わたしにとって新潟は、そんな多様な視点を持つための「原風景」のような存在なのかもしれない。
あの雪の白さも、日本海の夕日も、信濃川の流れも、すべてが今のわたしを形作る大切な要素なのだ。
東京と新潟、それぞれの魅力(私見)
- 東京の魅力
- 多様性: 様々な価値観や文化に触れられる。
- 利便性: 交通網が発達し、何でも手に入る。
- 刺激: 新しい情報やトレンドが常に生まれる。
- 新潟の魅力
- 自然: 豊かな自然に囲まれ、四季を感じられる。
- 食: 美味しいお米や新鮮な食材が豊富。
- 安心感: 温かい人間関係と、ゆったりとした時間。
どちらの街も、わたしにとっては大切な場所だ。
7. 思い出ではなく、今も生きている場所
わたしにとって新潟は、単なる「思い出の場所」ではない。
もちろん、幼い頃からのたくさんの記憶が詰まっているけれど、それ以上に、今もわたしと共にある、生きている場所だと感じている。
帰省が「ただの一時帰宅」ではない理由
年に数回、新潟に帰省する。
それは、単に実家に顔を出すというだけではない。
友人たちと再会し、馴染みの店を訪れ、変わらない風景に安心し、そして少しずつ変化していく街の姿を発見する。
そのすべてが、わたしにとって今の新潟とのつながりを再確認する大切な時間だ。
過去の思い出に浸るだけでなく、今の新潟を感じ、未来の新潟を想像する。
だから、帰省は「ただの一時帰宅」ではなく、わたし自身の現在地を確認するような意味合いも持っている。
新潟との関係性は変化しながら続いていく
これから先、わたしと新潟との関係性がどうなっていくのかは、まだわからない。
もしかしたら、いつかまた新潟で暮らす日が来るかもしれないし、そうではないかもしれない。
けれど、どんな形であれ、新潟がわたしにとって特別な場所であることに変わりはないだろう。
離れていても、心の中にはいつも新潟の風景があり、それがわたしを支えてくれている。
そして、その関係性は、きっとこれからも変化しながら続いていくのだと思う。
それはまるで、Spotifyのプレイリストのように、その時々の気分や状況に合わせて、お気に入りの曲を選び直す感覚に似ているのかもしれない。
変わらないメロディーもあれば、新しく加わるハーモニーもある。
そんなふうに、わたしと新潟の関係も、柔軟に、そして豊かに続いていけばいいなと思う。
まとめ
ここまで、わたしが新潟を好きな7つの理由について綴ってきた。
雪の静けさ、地元スーパーの賑わい、商店街の温かさ、地味さがくれる自由、美しい水と空、東京から見えた輪郭、そして今も続く関係性。
これらは、わたし個人の非常にパーソナルな「好き」のかたちだ。
けれど、もしかしたら、この文章を読んでくれたあなたの中にも、あなた自身の「地元」に対する同じような、あるいはまったく違う「好き」の感情が揺り動かされたかもしれない。
新潟を「好き」と言うこと。
それは、一つの言葉では語り尽くせない、たくさんの感情の重なりであり、時には揺らぎも伴うものだ。
それでも、わたしはこの街が持つ独特の空気感や、そこに流れる時間を、これからも大切に紡いでいきたいと思う。
この記事が、あなた自身の「地元」との関係性を見つめ直す、小さなきっかけになれたら、それ以上に嬉しいことはない。
Q&A:新潟についてもう少し知りたいあなたへ
Q1. 新潟市以外でおすすめの場所はありますか?
A1. たくさんありますが、個人的には「佐渡島」は一度訪れてほしい場所です。
豊かな自然と独自の文化が息づいていて、金山やトキの森公園など見どころも多いですよ。
また、温泉が好きなら「月岡温泉」などもおすすめです。
エメラルドグリーンの硫黄泉は美肌効果も期待できると言われています。
Q2. 新潟の冬の暮らしで大変なことは何ですか?
A2. やはり雪ですね。
特に大雪の年は、雪かきが毎日の日課になりますし、交通機関が乱れることもあります。
ただ、その分、雪国の知恵や助け合いの精神も育まれていると感じます。
最近は除雪設備も進化していますし、昔ほど大変ではないかもしれませんが、それでも雪との共存は新潟の暮らしの大きなテーマです。
Q3. 新潟の人はどんな人が多いですか?
A3. 一言で言うのは難しいですが、一般的には真面目で粘り強いと言われることが多いかもしれません。
雪国特有の忍耐強さがあるのかもしれませんね。
また、お米やお酒が美味しい土地柄か、食に対してこだわりがある人も多い気がします。
そして、どこかシャイだけれど、一度打ち解けるととても温かい人が多い、というのがわたしの印象です。
関連リンク
新潟ハイエンド体験・観光スポット
こんにちは、大井と申します。新潟育ちのアラサーです。これまで新潟県内にある様々な魅力的な体験や観光をしてきました。